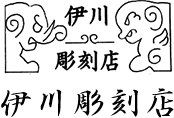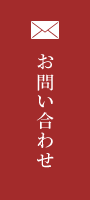木彫りの兜をお求めなら!五月人形の基礎知識を解説
五月人形の兜なら、伊川彫刻店の木彫りの兜をご購入ください。伊川彫刻店では、職人が一つひとつ制作した兜を販売しております。表札や看板などオーダーメイドのご依頼にも対応可能です。
男の子が誕生したら、五月人形や鯉のぼりを購入するご家庭も多いのではないでしょうか。この記事では、五月人形に関する基礎知識を解説いたします。
内飾りと外飾りについて、五月人形は受け継ぐことができるのか、誰が購入するのか、お手入れ方法などをご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
【木彫り兜】五月人形の基礎知識!内飾りと外飾りとは?五月人形は継承NG?
五月人形は、端午の節句の飾りものの一つです。同じように端午の節句に飾るものとして知られているのが鯉のぼりです。五月人形は内飾り、鯉のぼりは外飾りと呼ばれ、それぞれ異なる意味を持っています。
この記事では、内飾りと外飾りの詳細や五月人形は受け継いでもいいのかどうかなど、五月人形に関する基礎知識を解説いたします。
【木彫り兜】内飾りと外飾り

端午の節句に飾るものといえば、五月人形と鯉のぼりが有名です。
五月人形は「内飾り」、鯉のぼりは「外飾り」と呼ばれ、それぞれ飾る目的が異なります。
内飾り
その名のとおり室内に飾るもので、五月人形と呼ばれる飾りを指します。五月人形には鎧や兜などの甲冑飾り、武者人形などがあります。
内飾りは、子どもの健やかな成長を願って飾られるものです。武士の防具である鎧や兜は、子どもを厄災から守ってくれるお守りのような意味合いがあります。また、武士が戦いの際に身に着けるものなので、強くたくましく育ってほしいという思いも込められているのです。
外飾り
鯉のぼりや武者絵幟(むしゃえのぼり)など、屋外に飾るものを指します。
端午の節句の飾りとして有名な鯉のぼりは、立身出世の象徴でもある鯉を飾ることで、子どもの健やかな成長と出世を願うものです。また、神様に男の子が誕生したことを知らせるという意味もあります。
端午の節句に鯉のぼりを飾るようになったのは江戸中期からで、その頃は黒い鯉(真鯉)一匹だけでした。明治時代には赤い鯉(緋鯉)も一緒に飾られるようになり、昭和30年代には真鯉を父、緋鯉を母に見立て、青や緑などの鯉も一緒に飾られるようになって現代の形になりました。
昔はこの内飾りと外飾りを両方飾ることが多かったのですが、近年はアパートやマンションなどにお住いの方も多く、飾るスペースがないからと購入しない方も少なくありません。
しかし、そういった住まいの変化に合わせて、コンパクトなサイズの五月人形や鯉のぼりも増えてきています。
お店によってはオーダーメイドも可能なので、ぜひチェックしてみてください。
木彫りの兜や、看板をお探しの方は伊川彫刻店をご利用ください。伊川彫刻店では、職人がオーダーメイドで一つひとつ丁寧に木彫りの看板や兜を制作いたします。下のボタンよりこれまで制作した木彫り作品をご覧いただけます。
【木彫り兜】五月人形は受け継いでもいい?

五月人形は一生ものなので、高価な商品も多くあります。そのため、男の子の兄弟で一つの五月人形を共有したい、父親のものをそのまま飾りたいという方もいらっしゃるかと思います。
しかし、基本的に五月人形は一人に一つが理想で、他の人と共有したり、受け継いだりすることはいいことではありません。
その理由は、五月人形を飾る理由にあります。
前項で、五月人形は子どもを厄災から守る意味合いもあるとご紹介しました。
人形は人の厄を身代わりとして背負ってくれるものなのです。それを受け継いでしまうと「厄を受け継ぐ」ことになってしまうのです。
そのため、父親のものを受け継いだり、兄弟で一つのものを使ったりするのは控えるようにしましょう。
スペースの都合上何個も飾れないのであれば、コンパクトなサイズ感のものを選んだり、お兄ちゃんには兜、弟には武者人形など、違う五月人形を購入したりすることもおすすめです。兄弟のものや父親のものを一緒に飾るのは問題ありません。
また、五月人形は基本的に子どもが無事に成長したら役目を終えるものです。長年見守ってくれた感謝の気持ちを込めて、しっかり供養するようにしましょう。
長く使える高品質な五月人形をお探しなら、伊川彫刻店でご購入ください。
伊川彫刻店では、職人が一つひとつ丁寧に木彫りの兜を制作しております。オーダーメイドにも対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
また、オーダーメイドは兜以外の商品でもご依頼いただけます。表札・看板・オブジェなど、様々なオーダーメイドに対応いたします。世界に一つだけの表札や看板など、木彫りのオリジナル作品がほしいという方は、ぜひご依頼ください。
【木彫り兜】五月人形の基礎知識!誰が購入する?お手入れについて
兜などの五月人形を購入する際、誰が購入するべきなのか、お手入れはどうしたらいいのかなど気になる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、五月人形の基礎知識として、誰が購入するのか、お手入れ方法やしまい方などを解説いたします。
【木彫り兜】五月人形は誰が購入するもの?
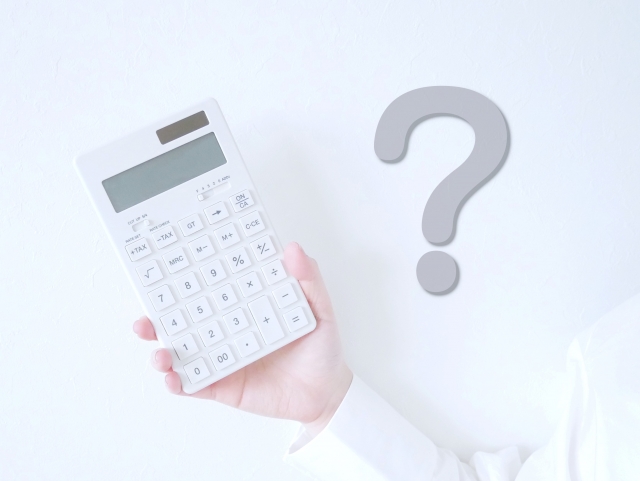
五月人形は誰が購入するのか決まりはあるのでしょうか。
一般的には、母方の祖父母が購入することが多いといわれています。それは、節句人形は母方の実家が購入する風習があったことが関係しています。
昔は妻が夫の家に入り、夫の両親と同居するという形が一般的でした。そのため娘が嫁に行ってしまうと両親はなかなか会えなくなるため、孫が生まれると節句人形を購入して会いに行くことが多かったのです。
しかし、現代では妻が夫の両親と同居するというケースも少なくなっているため、なかなか会えないということもありません。
そういった時代の変化もあり、現代では誰が購入するといった決まりはなくなっています。
注意したい点は、誰が購入するのかは地域によっても認識に差があるという点です。例えば、北海道と関東では父方の祖父母が、関西と九州では母方の祖父母が贈ることが多いといわれています。市町村単位や家庭によっても認識が異なるため、事前に話し合っておくことが大切です。
夫婦で子どものために購入する他、両家の祖父母で折半したり、内飾り(五月人形)と外飾り(鯉のぼり)で分担して贈ったりと様々なケースがあるため、それぞれのご家庭の事情に合わせて購入することがおすすめです。
【木彫り兜】五月人形のお手入れのポイント

五月人形は、職人が一つひとつ手作業で制作している高価なものも多くあります。また、毎年飾っていくものなので、長く美しさを保つためにも、お手入れが欠かせません。ここでは、お手入れのポイントについて解説していきます。
手袋が必須
手の脂や汚れがついただけでも、変色や劣化につながる可能性があります。五月人形を出し入れしたりお手入れしたりする際は、汚れがつかないよう手袋をつけるようにしましょう。
ホコリを除去する
水洗いや水拭きができるものではないため、ホコリや汚れを落とすということがお手入れのメインになります。しまう際はもちろん、飾っている間も定期的にホコリを除去するようにしましょう。
直接触れるのではなく、羽ばたきや筆などを使ってホコリを落としてください。
細かい隙間や、衣装についているホコリまで落とすことが重要です。
金具を拭く
金具の部分はホコリを落とすだけでなく、乾いた柔らかい布や眼鏡拭きなどで汚れを拭き取るようにしましょう。強くこするのではなく、指でぬぐうように優しく拭くことがポイントです。
適切な方法でしまう
保管している間に傷んでしまわないよう、しまい方にも注意が必要です。
ホコリや汚れがないかを確認しながら、もともと入っていた袋などにしまいます。柔らかい布や紙で包むのもおすすめです。その後は、汚れ・破損・虫から守るために、ポリ袋に入れて密封しましょう。最後に箱にしまって、湿気の少ない場所で保管してください。
木彫りの兜の制作依頼なら!表札・看板のオーダーメイドにも職人が対応
単語の節句に飾るものといえば、五月人形と鯉のぼりが有名です。
五月人形は内飾り、鯉のぼりは外飾りと呼ばれ、それぞれ飾る意味があります。兄弟で共有したり、父親のものを受け継いだりすることはできないため、男の子が誕生したら、一人に一つ用意するようにしましょう。
昔は母方の祖父母が購入する傾向にありましたが、特に決まりはないため、ご家族で話し合って購入することがおすすめです。
五月人形の購入をお考えなら、ぜひ伊川彫刻店でご注文ください。
伊川彫刻店では、木彫りの兜などを販売しており、職人が一つひとつ手作業で仕上げております。オーダーメイドのご依頼にも対応可能です。
オーダーメイドは兜だけでなく、木彫りの表札や看板、オブジェなども制作いたしますので、お気軽にご依頼ください。
オーダーメイドで木彫りの兜の制作依頼をお考えの方におすすめの記事
オーダーメイドで木彫りの兜の制作を依頼するなら伊川彫刻店へ!
| 店舗名 | 伊川彫刻店(IKAWA sculpture) |
|---|---|
| 代表 | 伊川 昌宏(IKAWA MASAHIRO) |
| 住所 | 〒770-0866 徳島県徳島市末広3−1−56 |
| 電話番号 | 088-653-5315 |
| FAX番号 | 088-653-5315 |
| メールアドレス | info@hori-masa.co.jp |
| URL | https://www.hori-masa.net/ |
| 営業時間 | 8:00~18:30 |
| 定休日 | 日曜日 |